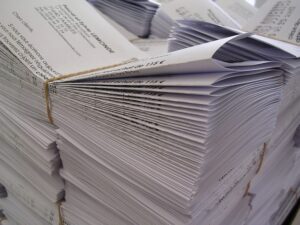AIは『WEB』の鏡

"AI"へ電子契約において立会人型電子署名と当事者型電子署名の違いは?と質問したところ、およそ次の返答。
立会人型電子署名と当事者型電子署名は、どちらも電子契約サービスにおいて文書の認証や承認を行う方法ですが(略)立会人型電子署名は、信頼性と法的な保証を重視する場合に使用され、当事者型電子署名は、一般的なビジネス取引や契約によく使用されます。(後略)
ChatGPT
逆なんですよね。これはクラウドサインさんなどがいかに多くのWEBコンテンツを用いて立会人型(事業者型と言った方が適切かもしれません)の啓蒙に努めていらっしゃるか、ということを如実に表してます。AIはWEBから勉強するんですから。
契約当事者が身元確認のうえ自身の電子証明書(言ってみれば電子のハンコ)を有償で取得して(ハンコを買って)、契約文書(PDF)への電子署名に付与する(ハンコをつく)のが当事者型。
それに対して、『電子契約サービス事業者の電子証明書』を付与するのが立会人型(事業者型)です。
否認を防止する意味合いでは、前者の方がより効果が高いと思われませんか?
誤解のないよう申しますが、事業者型を否定しているのではありません。むしろ、電子メールアドレスが正しく契約当事者のものであることを事前に確認したうえで、そのアドレスを用いた認証により署名するのならば、本人性の確認は厳に行われたということで否認防止の効果は同等かと思うんですね。
コンサルティングの中で、「電子証明書をわざわざ買うんですか?」と聞かれた時にわたしはこう答えてます。「それはあなた次第です」、と。会社がどう考えるかなんですね。年間でせいぜい1万円程度の証明書更新費用は、会社にとって必要コストと割り切ればそう高い出費ではないはずです。
ただし、契約は相手がいるもので、相手に同様の出費を求めるのかというのは、その契約文書をめぐる力関係が左右してくるところですよね。また、たくさんの契約文書を扱う会社では、事業者型の方が圧倒的に利便性が高いとも思います。
「あなた次第」の意味は、何の目的で電子化するのか、ということなんですね。お客様がモヤっとしていたらそこ(ゴール)を明確にしたうえで、電子契約サービスを選定していく必要があるということになります。